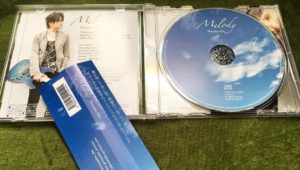お久しぶりです。
相変わらずの絶望的な更新頻度で恐れ入ります。
ここ1年ちょっとは、月平均15~20曲くらいの歌もの楽曲の作曲や編曲をやっています。作曲・編曲で仕事をする、という意味では、もう何年も前から「必要なことはだいたい身についている」と思っていたのですが、ハイペースである程度の期間やってみて初めて感じるようになった変化みたいなものもあります。
その一つが【「コード(進行)」という考え方はもういいんじゃないか】ということです。
「バークリーメソッド」の呪い
例えばジャズミュージシャンが演奏する場合、メロディラインとコード進行が書かれた譜面をみて演奏するのが主流ですが、このスタイルを「バークリーメソッド」と呼ぶそうです。
細かくは「コードに対して、そのコード上で演奏可能な音階(アベイラブルスケール)を基本として自由にメロディを生み出す」という考え方をもとにした音楽理論の体系のこと、でしょうか。
このバークリーメソッドは、ぼくの体験した限りでは、日本はもちろんアメリカでも、軽音楽の主流な音楽理論です。90%の人が、知ってか知らずか、これを軸に演奏や作曲をしているように思います。ぼくもそうです。
メロディの自由を奪うコード
ところが、ここ最近、例えば「C」というコード上で「EFEDC」というメロディを鳴らすことに違和感を感じるようになってきました。
バークリーメソッド的には「C」の上では、例えばCメジャースケールの音を使ってOKなんですが、Fの音がコード内のEと共存していることが嫌になってくるわけです。
コード「C」の上で「F」の音は、いわゆるアボイドノートと言われる音で、【ダウンビートには鳴らさないでね】とされている音です。逆にいえば、アップビートに鳴っている分には大丈夫だろう、と言われています。
……いや、大丈夫じゃなくない??
と思うようになってきたのです。少なくとも、無いに越したことはないだろう、という。
メロディがコードを補完する
というわけで、上記の例において伴奏に「E」音を入れない方がいい、ということにしてみます。
ロックギターの伴奏には、コードの1度と5度しか鳴らさないパワーコードみたいなものがあります。
これで曲が成り立つのは、メロディで1度と5度以外が鳴っているからじゃないかと考えられます。
「C」のパワーコードであるC音とG音の上で、先ほどの「EFEDC」というメロディを鳴らすと、細かくはありますが、事実上「C Csus4 C Cadd9 C」のようなコード進行になると考えられるわけですが、「C」と「Csus4」は共存できませんので、やはりここではパワーコードだけの伴奏がすっきりするなあ、と思います。
ちなみにこのEとFの衝突を避けよう、ということで、【Fの代わりにF#を使えばいいじゃん】というのが、バークリーメソッドに対してよく話題に上る「リディアンクロマティックコンセプト」という音楽理論体系の基本になるそうです。
まあ、「クロマティック」って言ってるから最終的にFも使うんでしょうけど。
全部モード的に考えてみる
ここまで考えてみて、なんかコードありきで考えるとやっぱゴチャゴチャするよな、と思いまして、いったんコードから離れようと考えました。
そもそも軽音楽の曲は、転調が起こらない限りはほとんどの場合メジャースケール一択なわけですから、もうこれは旋法(モード)ということでいいんじゃないの、と、思考は進みます。
「いやいや、ベースがルートっぽい音を鳴らしている時点で、コード的な機能が発生するでしょう。」
「え、別にベースラインもモードだってことで説明できるでしょうよ。」
ベースが曲に与える音韻的影響はとても大きいので、「それはさすがにないんじゃないの」と確かに思うのですが、でもあながちおかしいわけでもないな、と考える理由が;
例えば、ある一つのセクション最後のコードが「G」で、次のセクションの冒頭が「Em」みたいな曲は、軽音楽ではあまり書かないと思います(ベース以外の構成音が変わらず、変化を出せないため)が、「G」の次に「F」に進行するとしても、メロディによっては分数コード的な感じで「G」の次が「G/F」になることはアリかな、と感じます。でも、この場合もGコードの部分の構成音は全く変わらないわけですよね。
それなら、アリだ、と感じるのは、そういうベースの動きに慣れているだけなのかもしれない、と思いました。現代人ならではの慣れ、のような。
ベースだけで機能を感じるなら、それはもうコードじゃなくてモードということでいいですよね。
……いや、逆にベースだけでもコードの働きをしているわけだから、そこは逆にコードなのか。
??
もはやコードは考える必要がない
ベース音が変わることによってコード進行を感じるが、横軸(メロディック)の変化に対応するためにも、曲全体を大きく旋法的にとらえるのが良い、というか、ポップスとはそういうものだと考えられます!、ということが、最近考えていることです。
このように考えると、「3度邪魔だな……要らんか。」という判断がすぐにできるようになりました。というか、コードをほとんど考えなくなりました。
「メロがあって、ドラム打ち込んで、ベース弾いて、あとはメロとベースを邪魔しない音を適当に」という方針でしょうか。
最後になりましたが、管楽器や弦楽器のアレンジがどうも野暮ったくなる、というのも、コードの3度が入っていることに起因することがあるみたいです。
個人的には、3度の音はカッコ悪いとまで感じることがあるので使いたくないことも多いのですが、人によっては「どうしても3度を入れないと気が済まない」ようです。3度がないとハッキリしないから落ち着かないのでしょうか。そこがいいと思いますが。
どうですかね。